野洲観光物産にて絵葉書の販売

野洲市観光案内所(JR野洲駅前)にて、私の絵葉書を販売していただけることになりました。
野洲にお立ち寄りの際は、よろしければご覧ください。
■野洲市観光案内所
(JR野洲駅南口前)
営業時間:9:30から16:00(月曜休み)
TEL・FAX:077-587-3710
近江八幡スケッチ漫歩
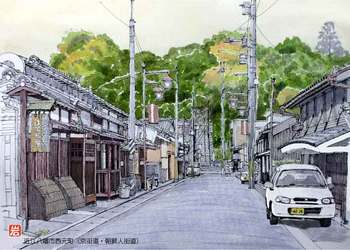
⑨近江八幡市西元町
西元町・西末町・北元町・北末町の4町は、明治維新までは総じて「寺内」といわれていました。
この地にある本願寺別院金台寺の門前町の意味です。
八万城形成時に、元々安土にあった同寺と東寺内・西寺内の両町の住民を移してできた町です。
現在の名称は町政の便宜上4分にしてこのように呼ぶようになりました。
近江八幡スケッチ漫歩
⑧近江八幡縄手町
縄手町と、変わった地名があります。徳川時代までは三丁縄手町と呼ばれており、わが国で
古くから用いられてきた土地区画制度の条里制に関連して、田地のあぜ道を示す呼び名が
もとになったものと考えられています。
八幡山城下の東入口にあたり、縄手入口橋(音羽橋)のたもとには木戸(黒門)が設けられていました。
この絵の下絵です。

完成画です。(スケッチ時間、40分)
縄手町と、変わった地名があります。徳川時代までは三丁縄手町と呼ばれており、わが国で
古くから用いられてきた土地区画制度の条里制に関連して、田地のあぜ道を示す呼び名が
もとになったものと考えられています。
八幡山城下の東入口にあたり、縄手入口橋(音羽橋)のたもとには木戸(黒門)が設けられていました。

この絵の下絵です。

完成画です。(スケッチ時間、40分)
近江八幡スケッチ漫歩
⑦ 岡田彌三右衛門邸跡(為心町)
初代は、慶長15年(1614)に北海道松前に渡り、呉服・大物などを商い、
後に漁場も手掛けました。5代目は、最大23もの漁場を請け負いました。
(小樽・古平の町を拓いた)11代目が壮年の頃、函館・室蘭に向かう道中
で、登山の山中で休憩した際に、川筋に湯気が立っているのを発見、これが
登別温泉だといわれています。

初代は、慶長15年(1614)に北海道松前に渡り、呉服・大物などを商い、
後に漁場も手掛けました。5代目は、最大23もの漁場を請け負いました。
(小樽・古平の町を拓いた)11代目が壮年の頃、函館・室蘭に向かう道中
で、登山の山中で休憩した際に、川筋に湯気が立っているのを発見、これが
登別温泉だといわれています。





